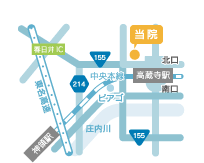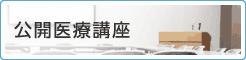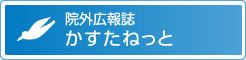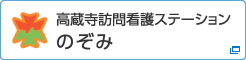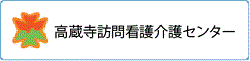厚生労働大臣の定める掲示事項
1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
2.入院基本料
各病棟では1日(日勤、夜勤合わせて)平均19人以上の看護職員と6以上の補助者を配置しています。
・療養病棟は、療養病棟入院基本料1を算定しています。
1日(日勤、夜勤合わせて)8人以上の看護職員と8人以上の看護補助者がいます。
・緩和ケア病棟は、緩和ケア病棟入院料2を算定しています。
一日(日勤、夜勤合わせて)8人以上の看護師を配置しています。
・ICUは、特定集中治療室管理料1を算定しています。
1日(日勤、夜勤合わせて)15人以上の看護師を配置しています。
・HCUは、ハイケアユニット入院医療管理料1を算定しています。 1日(日勤、夜勤合わせて)9人以上の看護師を配置しています。
3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化について
また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束の最小化についての基準を満たしております。
4.DPC対象病院
※医療機関別係数(包括評価に係る) 1.5711 ≪ 基礎係数 1.0718 + 機能評価係数Ⅰ 0.3734 + 機能評価係数Ⅱ 0.0812 + 救急補正係数 0.0447≫
5.入院時食事療養費(1)又は入院生活療養費(1)
また、6階東病棟では、患者さんに対して提示する複数のメニューから、お好みの食事を選択できる「選択メニュー」を実施しております。
6.基本診療料の施設基準等に係る届出・特掲診療料の施設基準等に係る届出
7.明細書発行体制
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるもので、その点をご理解いただき、ご家族が代理で会計を行う場合その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
8.保険外負担に関する事項
衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収はしておりません。
9.後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養
10.医療情報取得加算
11.医療DX推進体制加算
医療DXを通して質の高い医療を提供できるように、マイナ保険証の推進に取り組んでおります。
電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXに係る取り組みを実施しています。
12.歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
13.後発医薬品使用体制加算及びバイオ後続品使用体制加算
後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分安全な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、十分協議したうえで有効かつ安全な製品を採用しております。
また、医薬品の供給が不足した場合には、治療計画等の見直しを図るなど、患者様に不利益がないように対応致します。
なお、医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性がある場合は、対象の患者様に十分な説明をさせていただきます。
併せて、抗体製剤などのバイオ後続医薬品の使用にも力を入れています。
後続医薬品の採用におきましても、科学的根拠に基づいて採用しています。
14.勤務医の負担軽減及び処遇改善に関する取組事項
〇医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担
・初診時の予診の実施 ・静脈採血等の実施 ・入院の説明の実施
・検査手順の説明の実施 ・服薬指導
〇勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
〇予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
〇 当直翌日の業務内容に対する配慮
〇育児・介護休業法規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用
15.歯科外来診療医療安全対策加算
また、院内には自動体外式除細動器(AED)を常備しており緊急時適切に対処を行える体制を整えています。
16.院内トリアージ実施料
来院された患者様の重症度、緊急度を判断し、優先順位をつけて生命の危険な状態にある患者を早期に見つけだすことを目的としています。
17.外来腫瘍化学療法1
1.患者様からの電話等による緊急の相談に24時間対応できる連絡体制を整備しています。
TEL0568-51-8711(代表)
2.緊急時に入院できる体制を確保しています。
18.一般処方名加算及び長期収載品の選定療養費
一部の医薬品について製造販売業者の業務停止命令等の影響で後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、安定供給が難しい状況となっております。
つきましては、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
この一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
また、医薬品の供給状況や、令和6年10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養として自己負担が発生致しますのでご理解とご協力をお願い致します。
※一般名処方とは お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬から選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。